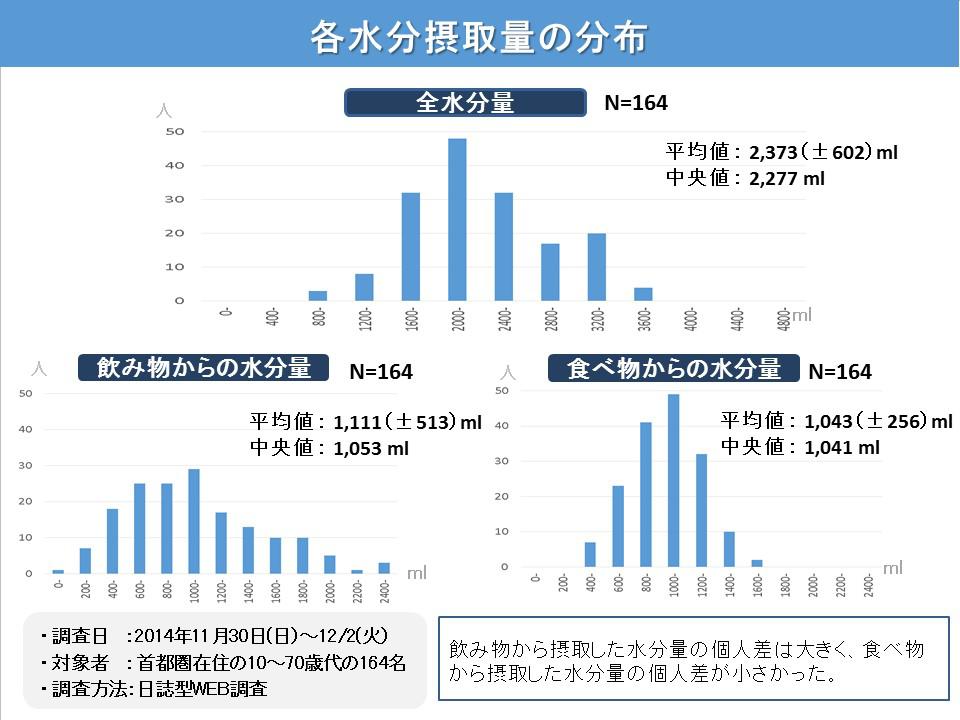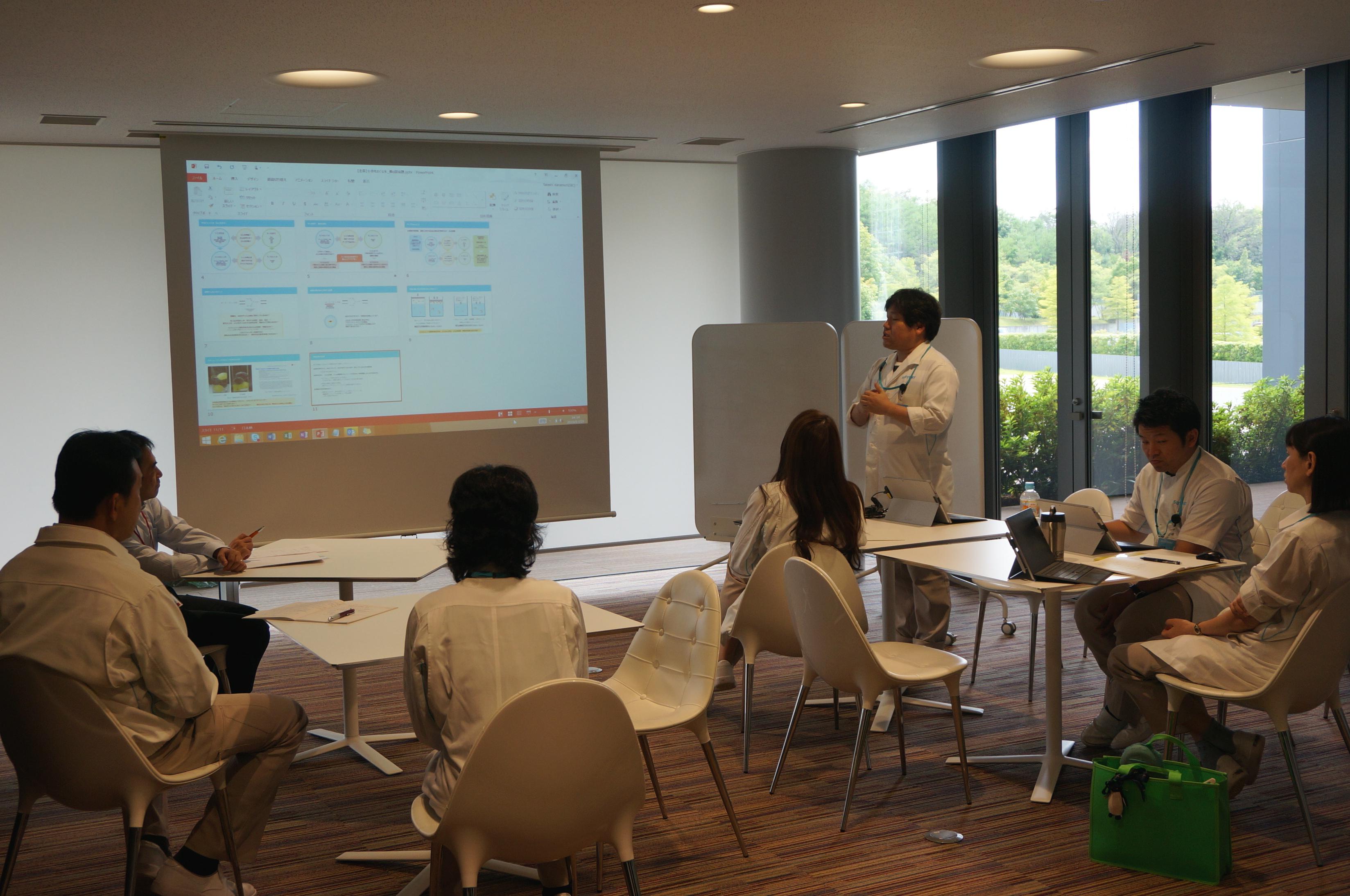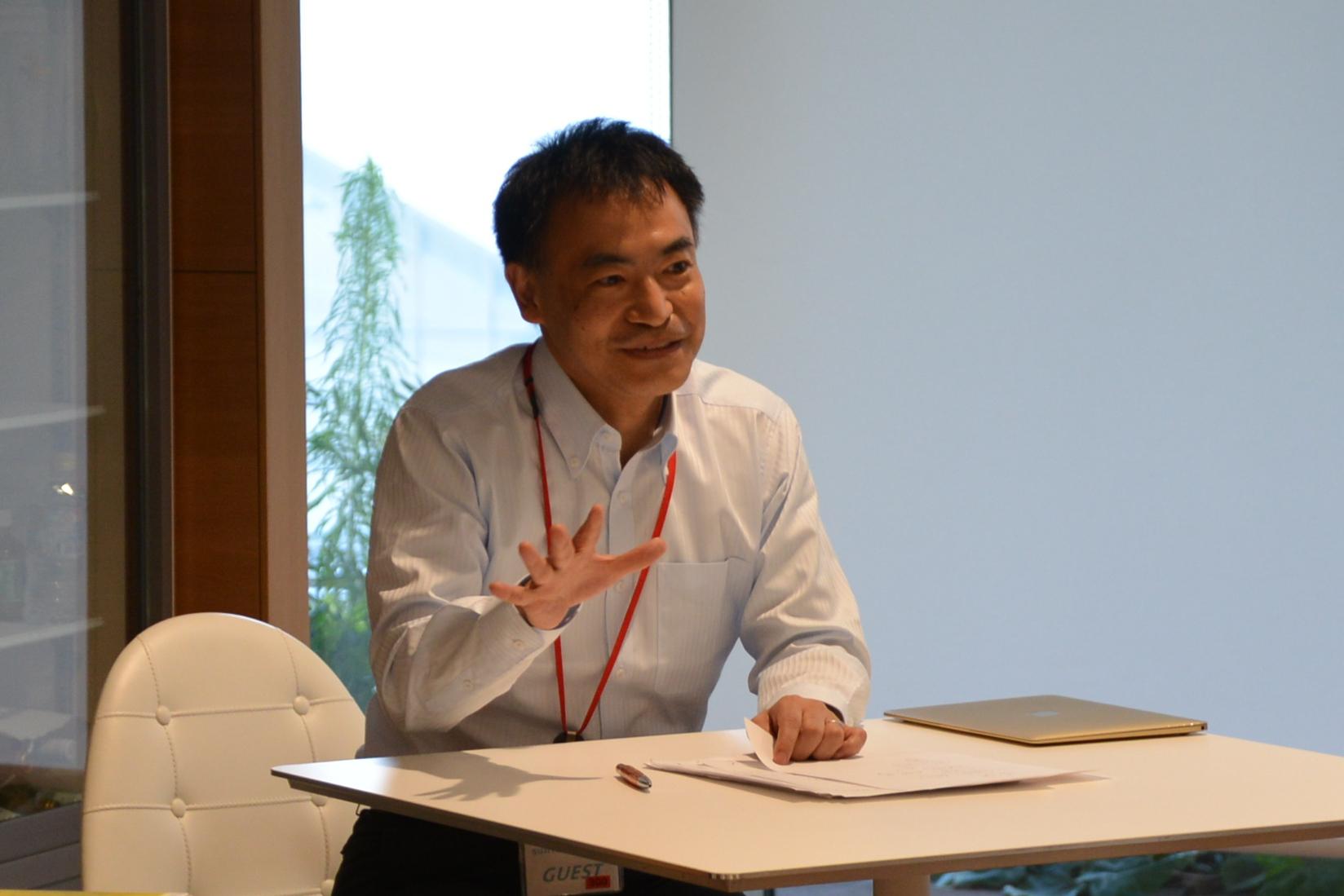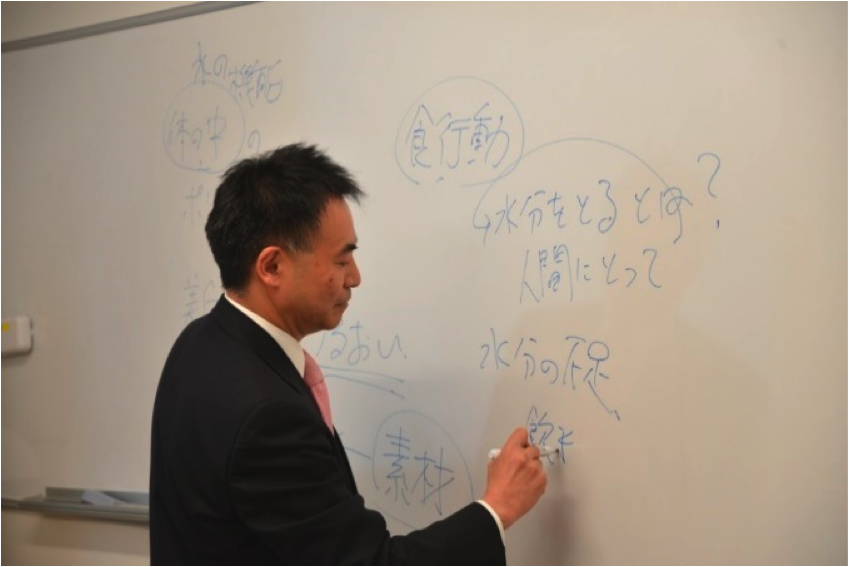第二回アクアフォトミクス国際シンポジウム
2016年11月26日~29日に、神戸大学百年記念館にて「第二回アクアフォトミクス国際シンポジウム」が開催されました。本シンポジウムの代表を務めたのは、「生命をめぐる水」プロジェクトに客員教授として参画する神戸大学ツェンコヴァ教授です。「生命をめぐる水」からは安井教授のほか、アクアフォトミクステーマやシミュレーションテーマを担当するメンバーが揃って参加し、それぞれの研究成果を発表しました。
会場となった神戸大学百年記念館は、エントランスから神戸の街が一望できる美しい建物です。六甲ホールと名づけられた大ホールに、世界中の大学・企業・研究機関から、アクアフォトミクスに関心を持つ研究者が集まりました。講演者の専門分野は、アクアフォトミクスを共通キーワードとしながらも「生体内の水の挙動」「素材と水の相互作用」「水分子の存在状態の解析」などと多岐に渡ります。それぞれの個性あふれる講演に加え、招待講演者のワシントン大学Gerald Pollack教授のお話は、水の新たな可能性を切り拓くような挑戦的なものであり、非常に中身の濃い講演会となりました。
シンポジウム期間中にはメインの講演会に加えて、一般向けのオープン講演会“水を科学する”が開催されました。また、アクアグラム作成やスペクトルデータ解析ソフトの公開といった、アクアフォトミクスの技術的な側面を掘り下げる講座も開催されました。質疑応答では、さまざまな専門分野の考え方が混じり合うような議論が会場を飛び交い、さらに多様な分野にアクアフォトミクスが発展していく可能性を感じました。当日のプログラムや関連情報は、アクアフォトミクスのホームページhttp://aquaphotomics.com/に公開されています。ぜひ、水と光が織りなす新しい科学の世界をご覧ください。
(執筆:沼田)