
![]()

![]()

![]()

![]()
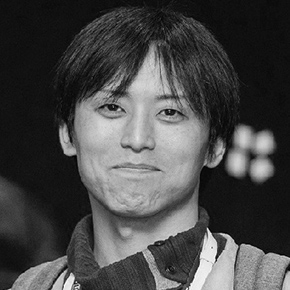



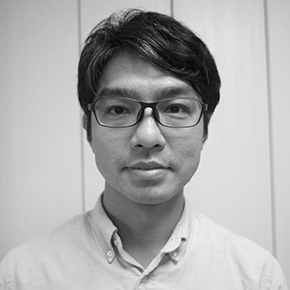



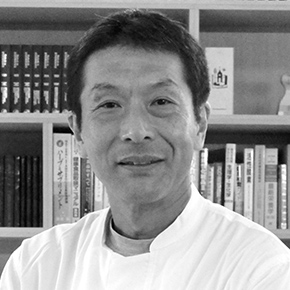

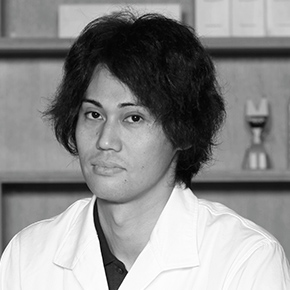




![]()

![]()

![]()
慶應義塾大学医学部 教授
安井正人Masato YASUI
1964年 東京都生まれ
主な経歴
慶應義塾大学医学部卒業
医師国家試験合格(1989)
東京女子医科大学 母子総合医療センター新生児室 助手(1992)
スウェーデン王国カロリンスカ研究所 大学院博士課程(1993)
Doctor of Philosophy 取得 (1997)
米国ジョンズホプキンス大学 医学部 講師 (1997)
同大学 助教授 (2001)
慶應義塾大学 医学部 薬理学教室 教授(2006)
学位
博士(医学)
専門
薬理学、小児科学
この研究に携わるきっかけ
「水と生きるSUNTORY」というコーポレートメッセージに惹かれて!
趣味と、そのエピソード
飲み会のノリで始めたトライアスロン。3種目あるので飽きやすい自分には最適です。2年前から始めたホットヨガ。最初は男性が少なく抵抗がありましたが、今では欠かせないエクセサイズとなりました。身体をめぐる水が促進しているような気がします?特にホットヨガ直後の水泳が最高!
慶應義塾大学医学部 客員教授
相馬義郎Yoshiro SOHMA
1960年 大阪府生まれ
主な経歴
大阪医科大学 医学部医学科 卒業(1987)
大阪医科大学大学院 医学研究科 修了(1991)
英ニューカッスル大学 医学部 リサーチ・アソシエイト(1991)
大阪医科大学 医学部生理学教室 助手・講師(1993)
米国ミズーリ大学 医学部 客員教授(2002)
米国ミズーリ大学 John M Dalton心臓血管研究所 主任研究員(2004)
慶應義塾大学 医学部薬理学教室 准教授(2008)
慶應義塾大学 医学部薬理学教室 客員教授(2017)
学位
博士(医学)
専門
膜輸送生理学、チャネルの分子生理・薬理学、医学生理学分野におけるコンピュータシミュレーション
この研究に携わるきっかけ
大学院生時代から膜輸送生理の研究を行なっていたところ、7年前に安井教授からWater Biology 研究会への参加の誘いがあった。
趣味と、そのエピソード
フライフィッシング(鱒の毛鉤釣り)
鱒は、山間部の冷たい水が流れる渓流に住んでいる冷水系の魚です。彼らは、複雑に変化し続ける川の流れのなかで、エネルギー消費を最小限にしつつ、流下してくる餌の水生昆虫を最も効率よく見つけられる位置に定位します。いい鱒を釣るためには、川の流れを読んで、どこに鱒が定位しているのかを予測して、毛鉤を投げなければならず、水の流れを読む力が釣果を大きく左右します。では、数多くの複雑な形状の細胞内小器官がつまった上皮細胞の中を水はどのように流れるのでしょうか。
趣味でも、研究でも、水の流れを読むのが私の仕事です。
(写真:グレイリング12 インチ 英国コッツウォルズ コルン川にて)
應義塾大学医学部薬理学教室 准教授
塗谷睦生Mutsuo NURIYA
1976年 東京都生まれ
主な経歴
東京大学理学部生物化学科 卒業(1999)
ジョンズホプキンス大学神経科学学科 博士課程修了(Ph.D. Neuroscience)(2004)
コロンビア大学、Howard Hughes Medical Institute博士研究員(2004-2007)
慶應義塾大学医学部薬理学教室 専任講師(2007-2016)
同准教授(2016)
横浜国立大学客員准教授(2012)
JSTさきがけ研究員(兼任)(2017)
学位
Ph.D. (Neuroscience)
専門
神経薬理学、多光子顕微鏡イメージング
この研究に携わるきっかけ
これまでずっと脳の研究、そして新たな切り口から脳の機能に光を当てる多光子顕微鏡の研究を行ってきました。
その中で、非神経細胞であるグリア細胞、そしてそれが制御する脳内の水環境の重要性が明らかとなり、更に多光子顕微鏡技術がその解明の鍵を握ることが分かり、現在の研究に至りました。
趣味と、そのエピソード
特に無いのですが、強いて言えば、料理と旅行などでしょうか。家族と一緒に色々なものを作って、それに合う好きなお酒と一緒に楽しむのが好きです。
慶應義塾大学医学部薬理学 助教
阿部陽一郎Yoichiro ABE
1965年 愛知県生まれ(ただけ)、茨城県育ち
主な経歴
筑波大学第二学群農林学類 卒業(1988)
筑波大学大学院修士課程医科学研究科 修了(1991)
筑波大学大学院博士課程医学研究科 修了(1997)
筑波大学基礎医学系 リサーチアソシエート(1997)
慶應義塾大学医学部薬理学 助手(1999)
慶應義塾大学医学部薬理学 助教(2007)
慶應義塾大学医学部薬理学 講師(2009)
学位
博士(医学)
専門
薬理学、分子生物学、神経科学
この研究に携わるきっかけ
筑波大学でポスドクをしていた時、新しいことにチャレンジしようと思い、実験医学に出ていた求人広告に応募し、西本征央前教授に採用されたことからアルツハイマー病研究に携わるようになりました。残念ながら西本教授は2003年に胃癌のため亡くなられてしまい、アルツハイマー病研究が続けられるかどうかという状況でした。2006年に安井正人教授が着任され、2007年より中枢神経系の恒常性の維持に関わると考えられるアクアポリン4に関する研究に従事することになりました。10年以上経過し、両研究が1つになりました。
趣味と、そのエピソード
音楽。リーマンショックの時にGibson Les Paulを買いました。
慶應義塾大学 医学部 薬理学教室 助教
安田充Mitsuru YASUDA
1983年 三重県生まれ
主な経歴
東京工科大学バイオニクス学部 卒業(2007)
東京工科大学大学院バイオニクス専攻 修士課程修了(2009)
東京工科大学大学院バイオニクス専攻 博士課程修了(2013)
東京工科大学応用生物学部 実験講師(2013-2014)
関西学院大学大学院理工学研究科 博士研究員(2014-2016)
関西学院大学理工学部 研究特別任期制助教(2016-2020)
慶應義塾大学医学部薬理学教室 助教(2020-)
学位
博士(工学)
専門
バイオ分析、バイオイメージング
この研究に携わるきっかけ
関西学院大学に所属していたとき、非破壊・非染色分析法である近赤外分光法やラマン分光法に出会いました。これらの振動分光法は、生体分子の分子構造情報のみならず、水分子の構造情報も同時に与えます。そこで、振動分光法を用いて水の観点から生命現象を調べようと思い、研究をスタートしました。
趣味と、そのエピソード
数年前に健康な体作りに目覚め、その第一歩としてウォーキングを始めました。それが習慣となり、今では1時間程度なら頻繁に歩きます。最近は筋トレも始め、筋肉痛との戦いが日課です。さらに、自身のカロリー摂取量を管理しており、週末には1週間分の弁当(1日2食)をまとめて作っています。
慶應グローバルリサーチインスティテュート(KGRI) 特任講師
慶應義塾大学医学部 訪問研究員
加藤靖浩Yasuhiro KATO
1975年 名古屋市生まれ
主な経歴
東京薬科大学 生命科学部卒業(1998)
名古屋大学大学院 生命農学研究科博士課程修了(2003)
日本学術振興会 特別研究員(2003-2004)
ジョンズ・ホプキンス大学 短期留学(2003)
東京歯科大学 研究員・非常勤講師(2004-2009)
慶應義塾大学 医学部助教(2009-2015)
北京大学 基礎医学院室長・客員准教授(2015-2020)
名古屋大学 学術研究・産学官連携推進本部 URA(2020)
学位
博士(農学)
専門
生化学、近赤外分光
この研究に携わるきっかけ
植物の耐塩性(水ストレス)機構の解明の研究から、生物の水チャネル(AQP)の研究に従事するため、2003年安井先生のラボに渡米したことがご縁です。
趣味と、そのエピソード
旅を通じて地元の美味しい食に出会うこと。そして、大自然を感じて滑るスキー。どちらも「水」がなくては生まれてこない、不思議なご縁を大切に歩んでいます。
慶應義塾大学医学部薬理学教室 助教
篠塚崇徳Takanori SHINOTSUKA
1984年 千葉県生まれ
主な経歴
東京理科大学 薬学部 薬学科 卒業(2009)
東京理科大学大学院 薬学研究科 薬学専攻 修士課程 修了(2011)
慶應義塾大学大学院 医学研究科 医学研究系専攻 博士課程 修了(2015)
東京大学大学院 医学系研究科 機能生物学専攻 特任研究員 (2016-2021)
学位
博士(医学)
専門
神経科学,多光子顕微鏡イメージング
この研究に携わるきっかけ
脳の中で水がどのように役立っているのかに興味を持ちました。
趣味と、そのエピソード
料理。簡単でおいしい料理(主におやつ)のレシピを試すのが楽しいです。
サントリーグローバルイノベーションセンター 研究部 上席研究員
村山宣人Norihito MURAYAMA
三重県生まれ
主な経歴
大阪大学薬学部薬学科卒業(1990)
大阪大学大学院前期博士課程卒業(1992)
サントリー株式会社入社 生物医学研究所(1992)
第一アスビオファーマ転籍(2005)
アスビオファーマ株式会社転籍(2007)
第一三共株式会社退社(2015)
サントリーグローバルイノベーションセンター株式会社入社(2015)
学位
薬学博士
専門
中枢薬理
この研究に携わるきっかけ
これまで中枢治療薬の開発研究に携わってきた際に、水分摂取量と認知症の関係について様々な仮説を耳にしました。血液成分中の水分含量の増加は、身体の健康、特に脳の健康に寄与する可能性があると思います。その仮説をストロングエビデンスで証明することが夢です。
趣味と、そのエピソード
京都に引っ越したのと、子育てがひと段落したのをきっかけに、毎週、家内と、大人の修学旅行と称して、美味しいご飯と、観光地や寺院をひとつ選択して、じっくり時間をかけて観光するのを愉しんでいます。何処で食べるのか、観光するのかを夕食時に話し合うのも楽しみです。
水科学研究所 所長
澤田元充Motomitsu SAWADA
大阪市生まれ
主な経歴
北海道大学農学部 農芸化学科卒業(1988)
サントリー㈱入社 分析センター(1988)
木曾川工場 品質管理(2000)
三得利(サントリー)中国品質保証センター 所長(2003)
高砂工場 製造技師長(2012)
北アルプス信濃の森工場 工場長(2017)
サントリーグローバルイノベーションセンター㈱ 水科学研究所 所長(2022)
学位
学士(農学)
専門
製品・原材料の品質保証、清涼飲料製造工程全般
この研究に携わるきっかけ
入社以来、お酒や清涼飲料の品質保証に関わる仕事に携わり、それらに無くてはならない水の品質保証にも関わってきました。その水が生体内に取り込まれ、どのように循環しているのかに興味があり参画しました。
趣味と、そのエピソード
テニス、登山、サイクリング、釣り、スキーなど基本アウトドア派です。また最近まで長野県北アルプスの麓に居を構えていました。北アルプスの麓から湧き出す水は本当に素晴らしいですよ。
サントリーグローバルイノベーションセンター株式会社 主幹研究員
鈴木寿栄Toshihide SUZUKI
静岡県生まれ
主な経歴
東北大学薬学部卒業(2008)
東北大学大学院薬学研究科修了(2010)
サントリーウエルネス株式会社入社(2010)
サントリーグローバルイノベーションセンター株式会社(2014)
学位
修士(薬学)
専門
薬理学
この研究に携わるきっかけ
存在が当たり前すぎて、視野から抜け落ちていた水。これまで自分がやってきた「健康」という切り口で捉え直そうと思います! (きっかけじゃないけど)
趣味と、そのエピソード
キャンプを15年ぶりくらいに再開しました。自然の中でテキトーに作る料理は楽しい。使うのは水道水ですが。
サントリーグローバルイノベーションセンター株式会社 主幹研究員
鈴木健Ken SUZUKI
1977年 神奈川県生まれ
主な経歴
東京大学工学部卒業(2001)
東京大学工学系研究科修了(2003)
サントリー㈱入社 プロセス開発部(2003)
サステナビリティ推進部(2009)
水科学研究所 主幹研究員(2020)
学位
修士(工学)
専門
水環境工学
この研究に携わるきっかけ
自然界の水循環を扱う研究を続けていましたが、体内を循環する水の科学も自然界の水循環と同じような深みのある研究分野であると感じました。解明すべき課題の多い分野ですが、一つずつこつこつと解き明かしていきたいと思います。
趣味と、そのエピソード
「パデル」というスペイン発祥のテニスに似たラケットスポーツにハマっています。長年続けてきたテニス仲間と始めたのがきっかけですが、テニス以上に戦略・戦術が勝ちに繋がると感じています。皆さんにもぜひ体験していただきたいです。
サントリーグローバルイノベーションセンター 水科学研究所
水間桂子Keiko MIZUMA
1964年 大阪府生まれ
主な経歴
関西学院大学文学部卒業(1987)
サントリー(株)入社 基礎研究所(1987)
洋酒事業部研究所(1996)
サントリービジネスエキスパート(株)水科学研究所(2011)
サントリーグローバルイノベーションセンター(株)水科学研究所(2013)
学位
学士(文学)
専門
嗜好科学
この研究に携わるきっかけ
これまでお酒や清涼飲料の味覚や嗜好の研究に携わってきました。その経験を活かして、水と健康に関する研究を進めていきたいと思いました。
趣味と、そのエピソード
趣味は映画観賞。新しいものをいろいろ見るというよりは、気に入った映画を何度も見てその世界に浸るのが好きです。
それと泳ぐことが好きです。時間がある時は2kmくらい泳ぎます。何も考えず誰とも話さずゆっくりと水に触れているのは、とても気持ちいいです。これも「水」ですね。
サントリーグローバルイノベーションセンター 研究部
中村友美Yumi NAKAMURA
1982年 石川県生まれ
主な経歴
奈良女子大学生活環学部卒業(2005)
奈良女子大学大学院人間文化研究科修了(2008)
慶應義塾大学医学部 特別研究助教(2009)
米国ミズーリ大学コロンビア校物理学 リサーチフェロー(2010)
サントリーホールディングス(株)入社 価値フロンティアセンター(2012)
サントリーグローバルイノベーションセンター(株)研究部(2013)
学位
博士(理学)
専門
食物科学
この研究に携わるきっかけ
食物や飲料を口にした後、体内で何がおこっているかということに興味をもち、これまで味覚やイオンの輸送についての研究をおこなってきました。その経験を活かし、生命活動に不可欠かつ体内で最も多い成分である『水』の体内での挙動を捉えることで新たな価値を見出していきたいと思いました。
趣味と、そのエピソード
ヨガで心と体をリフレッシュするのが好きです。ホットヨガで毎回大量の汗をかき、大量の水を飲み、改めて体をめぐる水を感じます。
最近は、神社めぐりも好きです。神社周辺には水にまつわる場所が多く、水の多様な価値観に触れて水の尊さを感じたりします。水の景観をただただ眺めるだけの時間も好きです。
サントリーグローバルイノベーションセンター
勝部諒Makoto KATSUBE
1993年 京都府生まれ
主な経歴
岡山大学農学部卒業(2016)
岡山大学大学院環境生命科学研究科修了(2018)
サントリーグローバルイノベーションセンター(株)入社 研究部(2018)
学位
博士(薬学)
専門
応用生物化学、糖鎖生物学
この研究に携わるきっかけ
新しい健康価値を生み出すことを通じて、お客様の笑顔に貢献したいと思い、日々研究しています。特に、水と健康の関係に強く興味を持っており、現在は年齢に伴い変化する水分率に注目しています。研究を進めるに当たって、身体をめぐる水への理解は必須です。入社して短い未熟者ですが、周囲の助けを借りながらプロジェクトに関わっています。
趣味と、そのエピソード
陸上、ワイン、食べ歩き、カメラ、旅行など。
新しい世界を知ることが好きで、最近は紅茶の勉強を始めました。ワインも同様ですが、香り豊かな飲み物はとても面白いです。紅茶の抽出に使う水はもちろん、サントリー南アルプスの天然水です。
